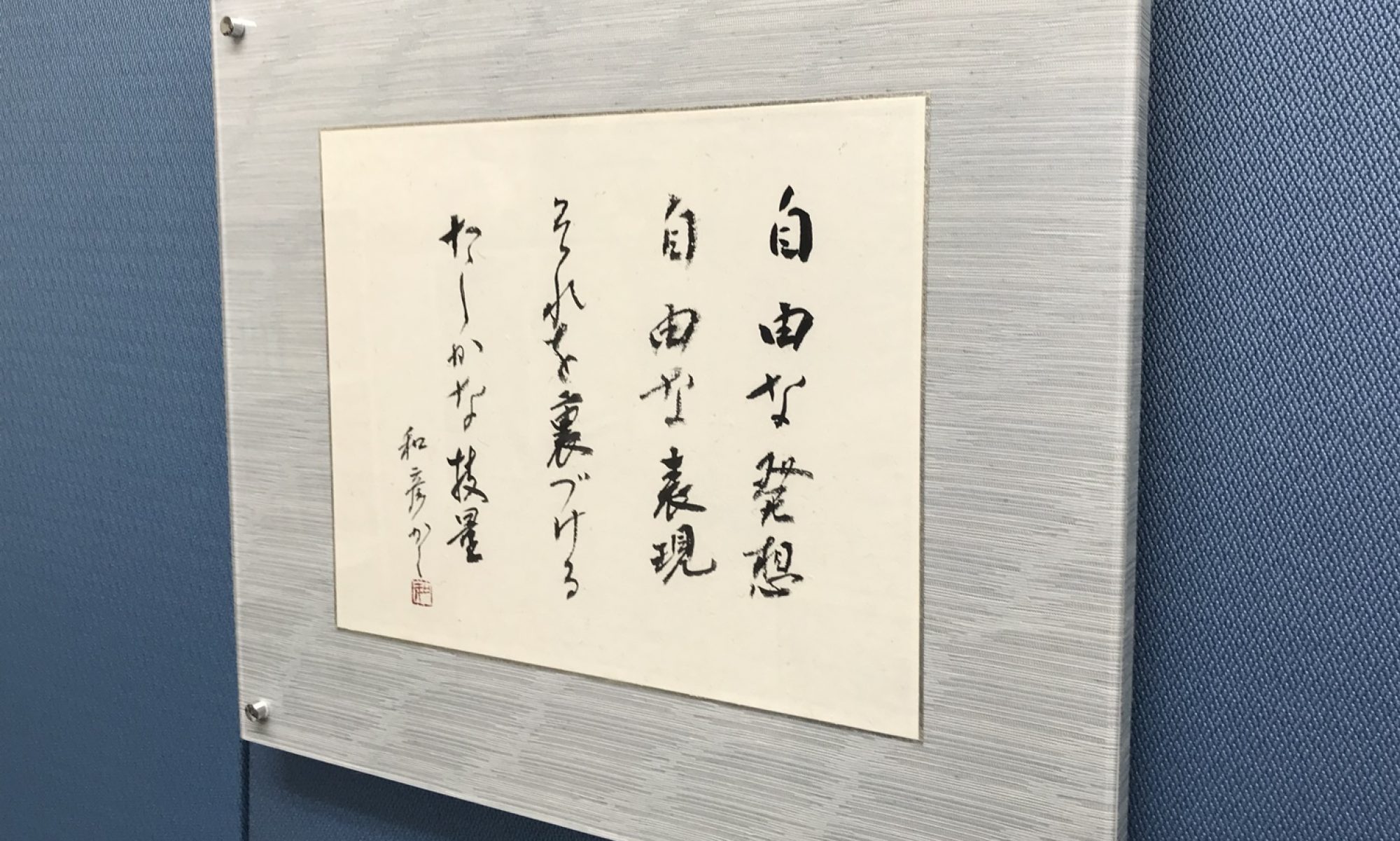あかいめだまの さそり
ひろげた鷲の つばさ
あをいめだまの 小いぬ、
ひかりのへびの とぐろ。
オリオンは高く うたひ
つゆとしもとを おとす、
アンドロメダの くもは
さかなのくちの かたち。
大ぐまのあしを きたに
五つのばした ところ。
小熊のひたいの うへは
そらのめぐりの めあて。
この歌は宮沢賢治の作詞作曲のものです。
皆さんの中にも知っている方が多くいると思います。
私は山や海に行き夜に満天の星を見るとこの歌を歌いたくなります。
いつぞや、朝日岳の山小屋で中年のおじさん方にこの歌を教え、岩魚の骨酒を飲みながらみんなで歌ったこともあります。また、月山の山小屋でも岩魚のお造りでビールを飲み飲み歌いましたね。
歌に出てくる“おおぐま座”は北極星の周りをぐるぐる回っています。
北斗七星はおおぐま座の腰とシッポです。
北極星は、“こぐま座”のシッポの先にある星なので、小熊はシッポの先を釘付けにされて、一年中ぐるぐる回っています。
歌の二番は、実際の星座の配置とは違いますね。北極星はこぐまの額の上ではなく、しっぽの先です。
歌は夜空を子どもたちが、北極星を目指してスキップをして星巡りをするのでしょう。
また、銀河鉄道に乗っての全天の星座見学の旅でしょうか。子どもたちのわくわくする気持ちが満ちています。
今まで書いてきた星は「恒星(fixed star)」です。
恒星とは太陽のように、自分で光を出せる星のことです。
天球上で位置を変えることがありません(長い長い時を重ねると動きますが)ので「恒」星と呼ばれました。
星座を形づくる星のほとんどは恒星です。
そこで、星座を覚えているといいことがあります。
まず季節の移り変わりが実感できます。
忙しい日常で季節など頭になかったときに、空を仰いで見るとオリオンが大きく輝いていれば、「ああ、もうすっかり冬なんだ…」と感じるわけです。“しし座”が勇壮に上ってくるのを見ると、「春ダナ…」心楽しくなります。
星座を媒介として、季節と心が一致します。
人生が豊かになります。
恒星は24時間で空を一周します。
これは地動説的な言い方です。
実際は地球が24時間で一回転するので、見える星座が動いて見えるわけです。全天は360度ですので、一時間では15度動くことになります。
その昔、閖上(ゆりあげ)の漁師に、
「船に乗ってイデ、時計などイラネ、ホスミロ(星見ろ)」と言われました。
若かった私は、「ホンダラ、ホスデデネドキ ドウスンノッシャ、」と聞くと、「ホンドキハ、スオミロ」というご高説でした。スオとは潮のこと。
これほど専門的でなくとも、夕方は東に見えた星座が西よりになったとすれば、国分町で飲みすぎたということになります。
また、世界的に見ると位置関係が分かります。
その地の緯度と経度によりある一定の時刻では星座の位置が違います
これは私には経験がないので外国のミステリー小説の話しです。
米ソの冷戦がすさましかった時、二重スパイがいました。ソ連に寝返ったといってかくまわれたスパイはアメリカの報復を恐れて外に出ませんでした。夜のみ散歩を短時間します。夜の九時きっかりに。スパイは空を見ていました。隠れ家を特定していたのです。アメリカに通報するために。その後の筋は忘れましたが … … 。
次は惑星の話です。
惑星とは自分で光をだせません。
太陽のまわりには9個の惑星がまわっていて、内側から水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星という名前がついています。
惑星は英語で(planet)といいます。
語源的には「さまよう者」「放浪者」の意味です。
惑星は恒星のように規則正しくは動きません。
空の恒星の間をうろうろと動きます。
金星や、土星、火星などは見ればすぐわかりますが、その他の星が、その日どこにあるかは天文年鑑で調べなければ分かりません。
平成24年12月12日、朝6時、早起きの私は二階のベランダで洗濯物干しをしていました。
すると、東南東の方角、地上から20度ぐらいのところ、金星と細い月の近くに、ホソボソと白く光っている星を見つけました。今まで見たことがありません。
“瞬いていない”、すると“惑星である”。
この星は水星(mercury)だ。私は確信しました。
事務所に出てから、仙台の天文台に電話しました。やはり水星ということでした。
私は感激しました。
水星は黄道(太陽の見かけの通り道)の近くを運行しています。
太陽に邪魔されてなかなか見ることができません。観測しにくい星です。
あのコペルニクスも死の床で「水星を見ることができなくて残念だ」といったそうです。
私はこの年になったが、死ぬ前に見ることができてよかったと喜び祝杯を挙げました。
旧暦で神無月(10月)29日、新月の前日でした。
スイセイでも違う彗星(comet)の話し。
今でこそ、彗星は水(氷)の固まりだなどと簡単言いえますが、昔の人々は恐ろしい思いをしたようです。
当時の記録が残っていて、人々の様子が分かるのはハレー彗星です。
それは、1910年(明治43年)のことです。 前年の1909年9月に発見されてからその軌道を調べると、1910年4月20日に近日点を通過した後、5月19日に地球に最接近し20日には彗星の尾の中を地球が通過することがわかったのです。
当時は彗星の正体は小型の天体であることは分かっていましたが成分は不明ですし、尾には毒ガスが含まれているらしいという風説が流れ「この世の終わりになる」のではという社会不安が広がっていきました。
学校の校庭で、子どもも大人も息を止める訓練をしたなど、いろいろあったようです。
ためらはず遠天(おんてん)に入れと彗星の白きひかりに酒たてまつる
斎藤茂吉 歌集「赤光」明治43年
(彦)