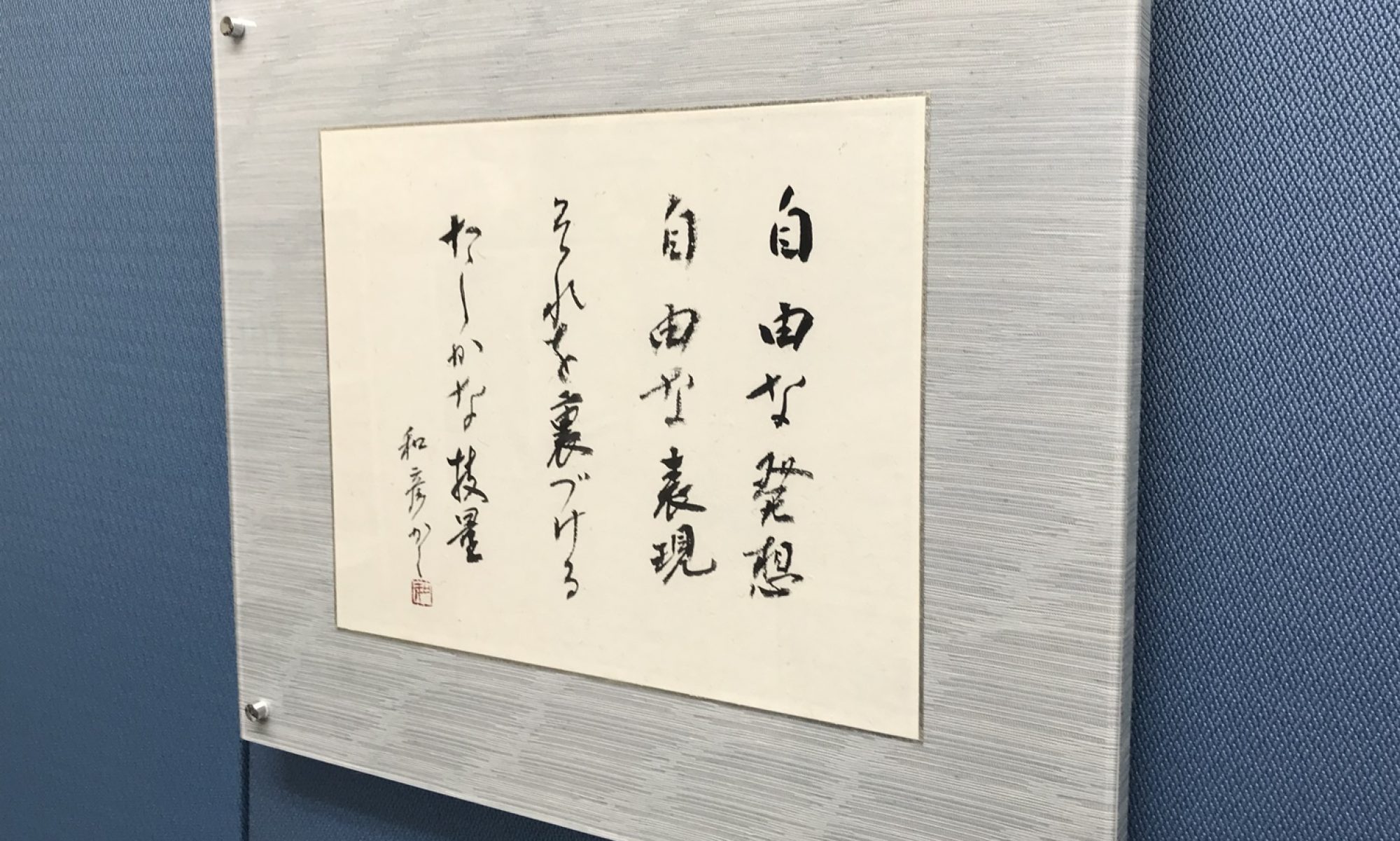山形県東根市に「六田」という地区があります。
東根市を南北にのびる国道13号線の東側に位置し、平行して走る県道沿いです。この県道は昔の羽州街道ですが、「六田宿」として栄えたところです。
ここは「六田麩(ふ)」と言われる「麩」の古来よりの名産地で、東根温泉の日帰り湯に行った折などに、「麩」を商う店が並んでいるのをご覧になった方もいらっしゃるでしょう。
六田宿は秋田藩佐竹の殿様が秋田と江戸を往復する際に立ち寄った地であり、俳人芭蕉が
「眉はきを俤(おもかげ)にして紅の花」
の句を詠うなど、文化や歴史が数多く残る地です。
過日街道歩きの交流会があり、六田の宿を歩く機会がありました。
「与次郎稲荷神社」与次郎は秋田の殿様に助けられた白狐の化身で、恩返しに飛脚に身を変え家来となり、秋田城から江戸屋敷までを六日間で往復したといわれています。
与次郎を不審に思う幕府の隠密に狙われ六田宿で命を落としたとされる伝説が残ります。
手厚く葬られた墳墓の地に神社を建て「与次郎稲荷」と崇められ、今でも飛脚与次郎の健脚はマラソンの神、商売繁盛、健康の神として参詣の客が多いのだそうです。
「佐竹井戸」の跡がありました。
佐竹の殿様に下々の水を飲ませたのでは恐れ多いということで、殿様専用の井戸を掘って水を供したそうです。
六田宿駅で使役する馬を差配する家の跡「元大馬喰くい」この家の前の畑からは馬の骨が今でもいっぱい出るそうです。
色々見て歩き、白水川の近くまで歩いてくると「関山古道」という案内がありました。
わたしはそれを見ていたく感動しました。
ここは仙台の人々が月山、羽黒山、湯殿山の出羽三山に参詣する時に通った道なのです。出羽三山に参詣する人々は「仙台道者」と言われていました。
関山は険しい道です。
関山を峰渡りして「六田宿」の入口の着くわけですが、その当時はこの古道の近くに“団子屋”や“ところてん屋”があったそうです。
そこで小腹を満たし、そこから寒河江のほうに向かい、六十里街道を通り大井沢又は本道寺の宿坊を目指したのでしょう。
宿坊のいる山伏の先達で三山の参詣をしたのだろうと、はるか昔を思い描きました。
三山参りをするときは通常数十軒の家で講を組み、一年で数人の代表者をくじで決めて参詣に送り出します。旅費はすべての家で出し合って積み立てていたものを充てるわけです。
20年ほどで全ての家が参詣を終えた時点で一旦講を解散します。この全世帯参詣を記念して出羽三山碑が立てられました。
仙台市内でも湯殿山とかを大書した大きな碑を見ることができます。
羽州街道は現在の国道113号、13号、7号にほぼ重なるコースで、福島の桑折町で奥州街道から分かれ、宮城の七ヶ宿、山形、秋田と進み、青森の油川でまた奥州街道に合流しました。
途中では上山や山形、天童、新庄、久保田、弘前の城下町を通っていました。
東根市の北に位置する村山市の熊野澤という地区があります。
湯野澤では熊野神社の大祭が10年ごとにあります。
そこでの見どころは“熊野神社奴振り”でして、
町内を江戸時代の参勤交代の時の奴さんの姿で練り歩くものです。
めでためでたの若松様よ 枝も栄える葉も繁る
そろたそろたよ奴振りそろた 秋の出穂よりまだ良くそろた
奴道具は、もとは東根市神町若木に居住していた士族日野家の所有でした。
江戸時代日野家は、秋田藩主佐竹候の参勤交代時の休息所で、日野家では参勤交代の時には六田と神町、神町と天童間を奴を振って先導していたといわれています。今は日野さんのお宅は歯医者さんです。
もっと北の新庄市(新庄宿)では、夏に新庄まつりがあります。
宵まつり・本まつりに絢爛豪華を競う山車(やたい)パレードは素晴らしく、藩政時代を偲ばせる歴史絵巻が繰り広げられます。
天満宮のご神体を収めて練り歩く “神輿渡御行列” が市内を一巡します。
新庄藩の武士になりきった、一対の挾箱を持つ足軽役二人の息のあった足さばきや傘廻しの妙技、熊の積毛を持つ伊達衆の演技(奴踊り)を、「下におろう、下におろう」の声を効きながら見ることができます。
斎藤茂吉は明治15年に現在の上山市に生まれました。
精神科医であり、文化勲章を受章した大歌人です。
戦後、大石田に疎開しました。
二藤部兵右衛門家の離れに2年程居住し、歌を詠み、散歩をするという生活をしました。
この時に生まれたのが、茂吉の最高傑作と言われる歌集「白き山」です。
昭和22年の作です。
封建の代の奴踊がおどり居る進み居る尾花沢往還のうへ