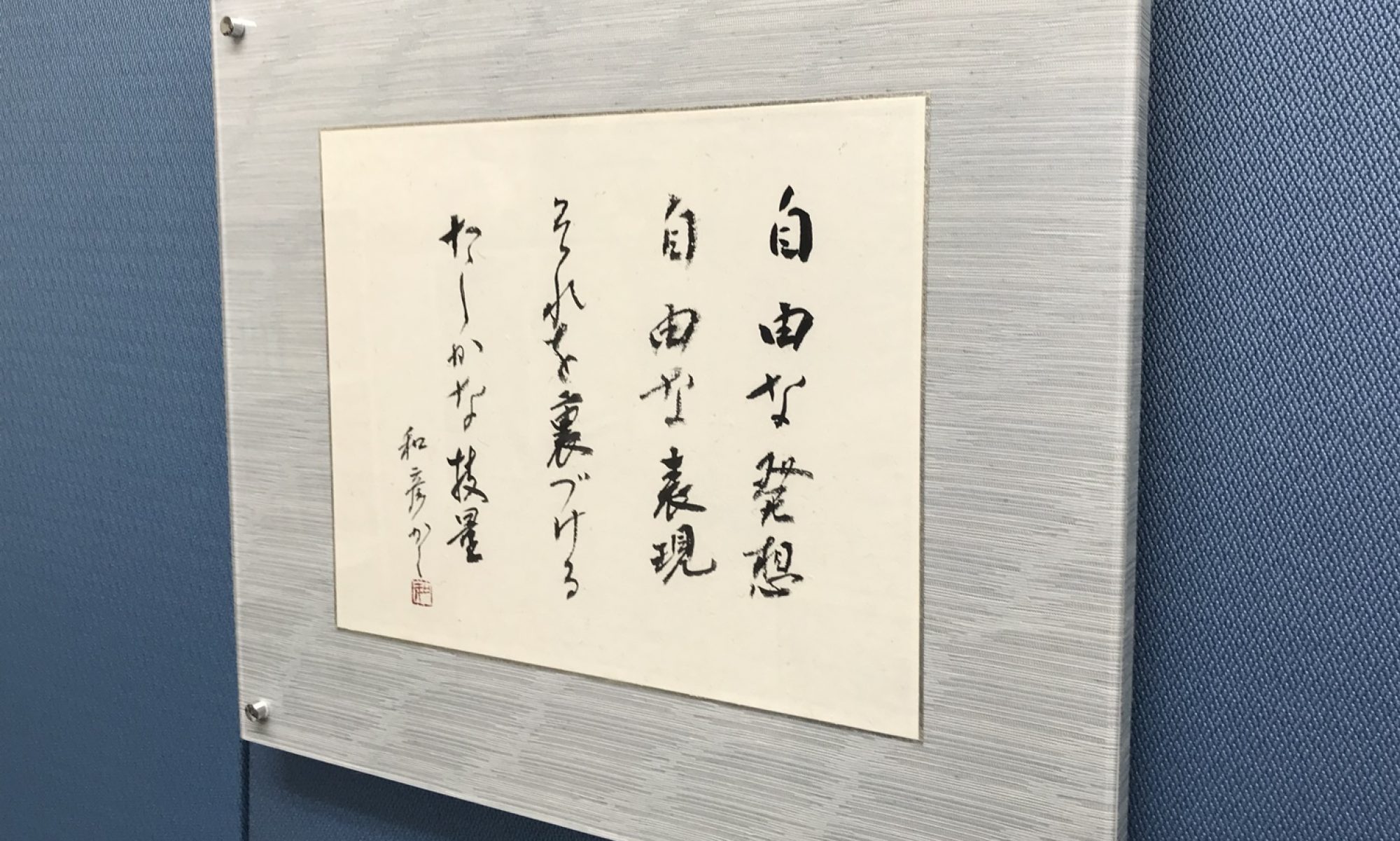寿永三年(1184年)、一ノ谷の合戦で源平が激突。義経による逆落しの奇襲で平家は総崩れになった。
源氏方の熊谷次郎直実(くまがいじろうなおざね)は、平家の大将軍を打ち取り手柄を挙げようと海辺に馬を進める。そこに、いかにも高貴な大将軍を思わせる武将が一騎、船に向かい海中に馬を進めていた。
直実は扇をあげて招くと武者は戻ってくる。渚に上がろうとしたところ、直実はむんずと組んで馬から落とし、取り押させて首を掻き切ろうとして、兜を外した。
年、十六,七歳の若者で薄化粧、歯を黒く染めていた。我が子と同じ位の年で、容貌も美しかったので、どこに刃を立てたらいのか分からなくなる。
… …
直実は我が子 小次郎の姿が重なり敦盛を逃がそうとするが、 後ろを見ると源氏の大群が迫っていた。
せめて自分の手で討ち取り、後世を弔おうと、直実は泣く泣く首を取るのだった。
若者の遺品を探ると一つの笛を見つけた。こうした合戦の場でも風雅な心を忘れない姿に東国武士はみな涙を流す。若者は平敦盛(たいらのあつもり)で、今年十七歳になったということが分かった。
敦盛が討ち死にの折に帯びていた笛は「小枝(さえだ)」である。「小枝」は祖父が鳥羽上皇から賜ったものを父が相伝して、敦盛に譲られたものである。
(平家物語 巻九「敦盛最後」)
熊谷草は源氏の熊谷次郎直実を、敦盛草は平氏の公達(きんだち)平敦盛
両方とも、花の形が源平時代の馬上の公達が流れ矢を防ぐために背に付けていた母衣(ほろ)に似ているところからそうみたのだろう。
母衣(ほろ)は、日本の武士の道具の1つ。矢や石などから防御するための甲冑の補助武具で、兜や鎧の背に、巾広の絹布をつけて風で膨らませるものである。
 (熊谷草)
(熊谷草) (敦盛草)
(敦盛草)
熊谷草は花や葉の様子もいかにも逞しい男の風貌を見せているのに対して、敦盛草の方は花の色や葉の形などを見ても、気品のある美しさを持った平家の公達を思わせるに十分な雰囲気を備えている。
そして両方ともに季節を同じく花を付けるので、人は源平の競い合った時代を想像して名付けたものだろう。
平家物語におけるこの一騎打ちの様子は、直実・敦盛を共に主人公として能の演目「敦盛」、歌舞伎といった多くの作品に取り上げられている。
また、明治時代に発表され親しまれた唱歌「青葉の笛」がある。青葉の笛とは、「小枝(さえだ)」である。
【1番】
一の谷の 軍(いくさ)破れ
討たれし平家の 公達(きんだち)あわれ
暁(あかつき)寒き 須磨の嵐に
聞こえしはこれか 青葉の笛
【2番】
更くる夜半(よわ)に 門(かど)を敲(たた)き
わが師に託せし 言の葉(ことのは)あわれ
今わの際(きわ)まで 持ちし箙(えびら)に残れるは「花や 今宵(こよい)」の歌
2番の歌詞について、登場人物は『平忠度(たいらのただのり)』で、二つの場面がうたわれている。
平家物語巻第七「忠度都落」
平家一門が都落ちしていく中、忠度(ただのり)は主従七騎で都に引き返し、歌の師匠である藤原俊成の邸にやってきた。
邸内は落人の訪問に騒然となる。しかし、俊成は忠度ならば、と対面し、忠度の勅撰集の入集を願う歌よみとしての思いを受け止める。忠度は和歌の巻物を託し、高らかに別れの朗詠を口ずさみながら、その場を後にした。
後に忠度の和歌は、俊成によって「詠み人知らず」として、千載和歌集に収められた。
さざなみや 志賀都は 荒れにしを 昔ながらの 山桜かな
平家物語巻第九「忠度最後」
一の谷の合戦において忠度(ただのり)は搦手の大将軍であった。源氏方に急迫されるや百騎ほどいた武者は逃げうせ、ただ一騎になってしまった。
最後は念仏を唱えつつ首を討たせた。最後まで名乗らなかったが、箙に一首の歌と「忠度」と書かれてあったことで、その名が判明。文武に優れた武将の死はみなから惜しまれた。
行(ゆき)くれて木(こ)の下かげをやどとせば花やこよひのあるじならまし