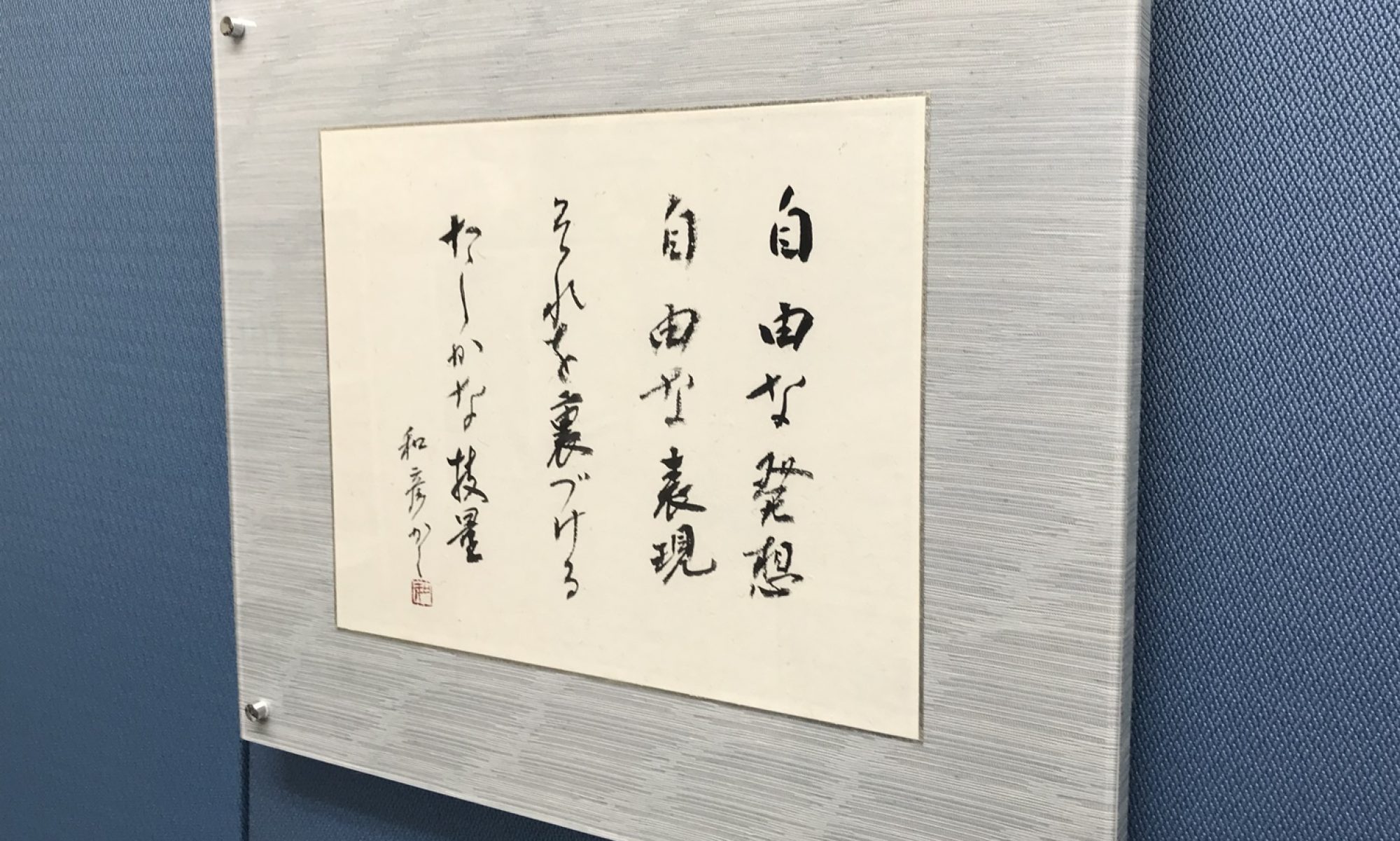事務所の棚に、事務所移転のお祝いにいただいた福升(1升枡)があります。
仙台市の秋保にある勝負の神様「秋保神社」のものです。

「福」「寿」の二字が書いてあり、「令和二年 庚子歳」とも書いていあります。
この「庚子」とは何か、それは東洋思想に基づく干支(えと)です。
この話は今年二月の移転早々に書けばよかったのですが、福升を使う節分も終わって季節外れの感もしないではないですが、先日あるニュースが新聞に出ていて、急に書くモチベーションが湧いてきました。

7月の末に我が若林区に猪が出現したそうです。
太白区の方から広瀬川に架かる千代大橋を通り四号線と井田浜街道の交差点を渡り、私の住んでいる上飯田の隣部落「沖野」に来たようです。河川敷には畑がありますので、ジャガイモでも食べに来たのでしょうか。
https://www.youtube.com/watch?v=paeAj25a7ZA
猪は古来より宮城県にいたようで、七ヶ浜の貝塚の資料館に行くと貝塚の中に猪の歯が入っているのを見ることができるので、縄文人も猪を食べたのだろうと分かります。
しかし、いろいろな事情があり、ついこの前までは宮城県では阿武隈川より南に生息し、北には進出していませんでした。
ところが東日本大震災により農作物に放射能の影響が出て、人も動物も食料にできなくなりました。
その為、鉄砲で撃たれる心配の無くなった猪は堂々と阿武隈川を渡り、仙台方面はもちろん県北まで生息範囲を広げていて、仙台でも食痕を見ることができます。
泉ヶ岳にあるレストランの前を親子で歩きまわったり、江合川を渡って鳴子の方まで進出しているとか、生息範囲を広げているそうです。

猪突猛進という言葉から猪年の人は“熱心で勇気のある人”と言われたりしますがどうでしょうか。
干支の順番を決める時に、いのししは猪突猛進に前だけを見て走っていたので、ゴールを通り過ぎてしまって、一番最後になってしまったそうです。
十二支は言うまでもなく、
子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥
の総称です。
ちなみに、普通「えと」と言うと、十二支を指すように使われていますが、干支と書くように「十干」と「十二支」の組み合わせになっています。
十干(じっかん)とは、
甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸
の10の要素からなります。
この十干に五行(木・火・土・金・水)を当てはめて、2つずつを木(もく、き)・火(か、ひ)・土(と、つち)・金(こん、か)・水(すい、みず)にそれぞれ割り当て、さらに陰陽を割り当てている。
日本では陽を兄、陰を弟として、例えば「甲」を「木の兄」(きのえ)、「乙」を「木の弟」(きのと)などと呼ぶようになりました。

さて、十二支に十干を組み合わせると干支、十干十二支(じっかんじゅうにし)になります。
組み合わせは10と12の最小公倍数ですから、60通りあります。
十二支は中国の紀元前の戦国時代に作られたと言われており、陰陽五行説に繋がります。
占いの道具としての設定されました。

東洋思想では未来は既に決まっているものであり、人はそれを知るすべを持たないのです。
まさに天の神のみぞ知るというわけで、東洋の占いは基本的には未来を知るためのものです。
東洋思想における時間は、未来から過去へと流れています。
天の神の大いなる意思によって未来は既に定められていのです。
それが我々の元に降りかかってくると考えます。
日本でも、昔、平安時代に高名な陰陽師(おんみょうじ)安倍晴明(あべのせいめい)がいました。
平安時代の貴族は、陰陽師の安倍晴明にお願いして、この先自分の身に降りかかってくる定められた未来の出来事を教えてもらい、それに備えようとしたのです。

還暦という意味は、もう一回暦が回ってきたという意味です。
「私のオジサンは還暦の一か月前に亡くなった、」という言い方は間違いです。
還暦は、60歳の「誕生日」に迎えるのではなく、60歳の誕生日がある年の元日に迎えるものなのです。
数え年で言えば61歳のお祝いです。
実際の干支を挙げましょう
・2019年 己亥(つちのとい・きがい)
・2020年 庚子(かのえね・こうし)
・2021年 辛丑(かのとうし・しんちゅう)
・2022年 壬寅(みずのえとら・じんいん)
・2023年 癸卯(みずのとう・きぼう)
枡に書いてある「庚子」の意味は、新たな芽吹きと繁栄の始まりです。
つまりは、新しいことを始めると上手くいく、大吉であると指し示しています。
素晴らしものを貰いました。
幸町のMさんに感謝です。